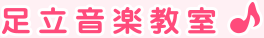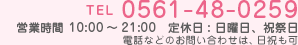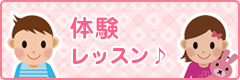音楽講座の翌日23日、コンサートはお昼過ぎからだったので、午前は金華山に行ってきました。
わたしは初の岐阜城でしたが、母は30年ぶりだったそうで…!
お城に行くのって大変ですよねえ…今はロープウェイがあるので山登りはしなくても大丈夫ですけど、それでも石の階段を登りました。こういうお城に行くと昔の人たちは体力あったんだろうなあと思います。
下の写真の赤い屋根の船はもしや鵜飼の…?鵜飼 間近で見てみたいです。

ロープウェイ降りてすぐのところにリスさんと触れ合えるリス村がありました!動物好きにはたまらんです。もふもふ。
さて、岐阜城観光のあとは待ちに待ったコンサートでした!
前日の音楽講座と同様にプレイエルとスタインウェイの弾き比べプログラム。バラードは今までスタインウェイで聴いたり弾いたりしていたので、特に違いを感じました。コーダの部分はスタインウェイで弾くと迫力があるのですが、プレイエルだと荘厳な感じがします。この楽器のことを考えると、フォルテと楽譜に書かれていても、ただバンバン音を出せば良いということではないんだなというのが見えてきました。きっと、ショパンより前の時代の作曲家は特にそうなんだろうなあと。コンサートも演奏法の解釈にとても役に立ちました。
コンサート後は仲道さんのコンサート恒例のサイン会。購入した仲道さんの書籍にサインしていただきました。コンサートのたびにサイン会に参加しています。仲道さんは物腰柔らかでふんわりとしている雰囲気で、演奏ももちろん好きですが、人柄も好きなのです。
サイン会のあとは、公開レッスンがあり、コンサートチケットで無料で聴講できたので聴いてきました。楽譜持参できなかったのでひたすらメモ書き…幸いにも舟歌以外は弾いたことがあったので、なんとなく楽譜は頭にありました。
仲道さんの奏法を見ていて、どんな脱力法なんだろう?といつも疑問に思っていたのですが、公開レッスンでフレーズ感についてお話しされているときに、手首ばかり使わない方法で脱力されているのが分かりました。落下も使っているのかな?私自身、重力を利用すると無理なく音を出せると考えています。特別体格に恵まれているわけではないため、弾くための工夫は欠かせません。指導するうえでも、子どもに伝えるための言葉がけの勉強にもなりました。
本当にとても充実した2日間でした(o^^o)
また仲道さんの演奏会が夏にあるので、楽しみにしています♪
講師 ♪ 足立わかな